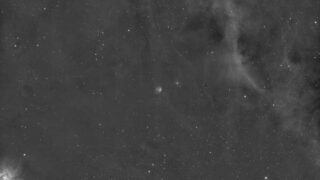 天体写真
天体写真 SQA106 M78 Hαでの撮影
色々と試行している中で、撮影しましたM78 Hαの画像です。試行と言ってもCRUX200MFでのTitanTCS PECに関して再検討しているだけですが。合成ではなくHαだけです。撮影条件:QHY600M、PhotoGraphic DSO ...
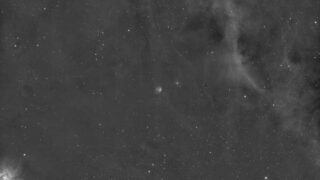 天体写真
天体写真 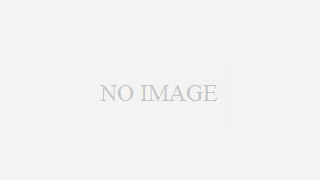 天体写真
天体写真  天体写真
天体写真 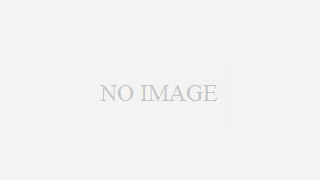 天体望遠鏡
天体望遠鏡 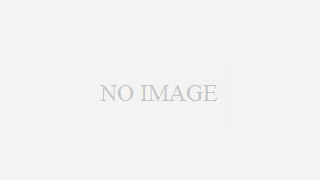 雑記
雑記  天体写真
天体写真  天体写真
天体写真 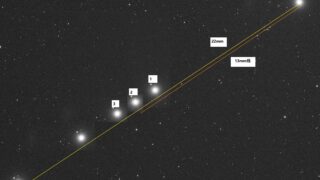 天体写真
天体写真  天体写真
天体写真  天体写真
天体写真